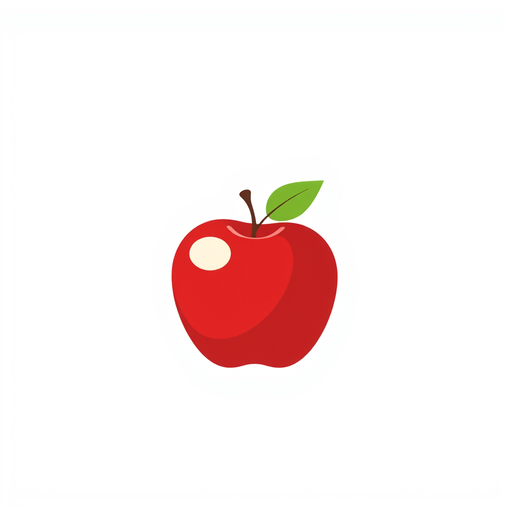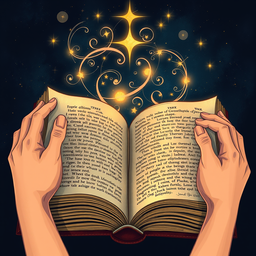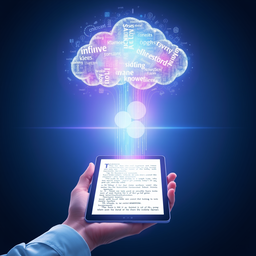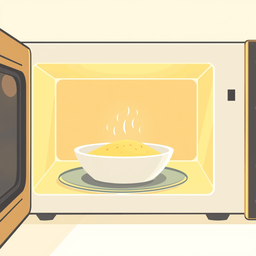2Dは描画パイプラインが単純で、同等解像度なら計算・電力コストが圧倒的に低い。
2Dレンダリングは基本的に「画素数にほぼ線形」の処理で済み、ジオメトリ変換・深度テスト・複雑なライティングといった3D特有の高負荷工程を回避できます。結果として、低スペック端末でも高フレームレートと安定したサーマル特性を両立しやすく、モバイルではバッテリー持続時間にも直結します。描画パスが短い分、入力から表示までの遅延も抑えやすく、操作レスポンスが明快です。性能の“天井”ではなく“底上げ”を提供できるのが2Dの強さです。
2Dアセットは容量が小さく圧縮効率が高いため、配信と起動が速い。
ベクター画像(SVG)はアイコン1つで5〜30KB程度に収まりやすく、等価解像度のPNG@3xは200〜500KB、3Dモデル+テクスチャは1〜10MB以上になることが珍しくありません。つまり同じ視覚情報を届けるのに必要な帯域とストレージが桁違いに少なく、CDNコストや初回ロード、パッチ配信の負担を大幅に削減できます。軽いアセットはメモリ圧迫も小さく、プロセス再起動やOSのメモリ回収に強い設計が可能です。配信の速さはそのままユーザーの離脱率低下に効きます。
2Dはデターミニスティックでバグ表面積が小さく、開発速度と品質が安定する。
陰影、GI、スキニング、法線・タンジェント、Zファイティングといった3D特有の不具合要因がなく、表示結果の再現性が高いのが2Dです。ピクセルパーフェクトな基準で自動テストを書きやすく、マルチプラットフォームでもドライバ依存の差異が出にくいのでCI/CDが素直に回ります。物理・当たり判定も2Dは状態空間が小さく、意図しない挙動のデバッグが短時間で済みます。結果としてイテレーションが速く、限られた工数を体験の磨き込みに集中できます。
2Dは可読性と制御性が高く、情報伝達の精度を最大化できる。
UIやデータ可視化では、位置・長さ・色の2D表現が最も誤読が少ないことがHCI分野で繰り返し示されています(3D化すると遠近・自己遮蔽で歪みが生じやすい)。ベクターやSDFはHiDPIでもシャープで、タイポグラフィやアイコンの“意図した形”をピクセル単位で保証できます。ノイズとなる不要な陰影や遠近を排し、視線誘導やアクセシビリティ(コントラスト・ヒットターゲット)を設計で完全に掌握できるのが2Dです。結果、ユーザーは速く正確に情報を掴み、誤操作も減らせます。