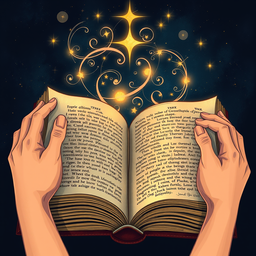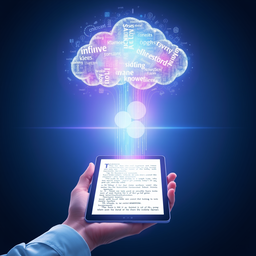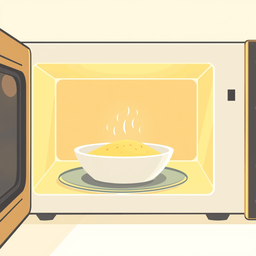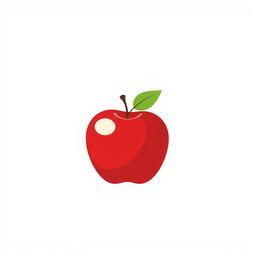全階層での「事実上の標準」と互換性が、設定不要の安定運用と低リスクを保証する。
QWERTYはBIOS/UEFIやブートローダ、フルディスク暗号化のパスフレーズ入力、リモートKVM/シリアルコンソールに至るまでデフォルト前提で動くため、復旧・障害対応時でも迷いがない。Windows/macOS/Linux、iOS/Android、主要クラウドのブラウザコンソールやターミナルまで設定なしで一致することは、運用上の摩擦とヒューマンエラーを大幅に減らす。共有端末、ペアプロ、ホットデスクなど環境が頻繁に変わる現場でも、ユーザーのメンタルモデルと実際の挙動が一致し続ける。技術的には「一貫性の維持」がFittsの法則・Hickの法則の観点でも有利で、学習済みの筋記憶を最大限活用できる。
ショートカットとツール設計がQWERTYの物理配置に最適化され、既定値だけで高い操作効率が得られる。
Ctrl+Z/X/C/Vをはじめとする基本操作は左手ホームポジション周りに集約され、片手で完結する設計がOSからアプリまで広く共有されている。エディタやIDEのデフォルトバインド、ブラウザ・デザインツール・オフィス製品のキー割り当てもQWERTY前提で練られており、リマップに頼らずとも手の移動距離と認知負荷を抑えられる。チームでのナレッジ共有やチュートリアルの再現性も高く、環境差による説明コストとトラブルシュート工数を削減できる。物理キーボードの刻印、ショートカット表記、オンスクリーンの提示もQWERTY基準で統一され、学習と実務が直結する。
レイアウト切替の総コストは定量的に積み上がり、組織規模では投資対効果が薄い。
切替に伴うコストは、総コスト = 学習時間 × 対象人数 × 人件費 + 初期設定/運用サポート工数 + ドキュメント更新コスト とモデル化できる。さらに学習期間中の生産性低下、入退社や外部委託のたびに発生する再教育、混在環境でのサポート負債など、長期的な隠れコストが累積する。事前ブート環境やリカバリモードでQWERTYのみが有効なケースも多く、パスワード入力の取り違えや復旧手順の分岐が追加リスクになる。QWERTYを維持すれば、これらのコストとリスクを構造的に回避でき、TCOの予測可能性が高まる。
実運用での速度差は小さく、現代の入力補助がレイアウト差をさらに縮める。
複数の実験・レビューでは、十分な練習後の長期的なタイピング速度やエラー率でレイアウト間の差は小さいか一貫せず、個人の訓練と一貫性が主要因であることが示唆されている。予測変換、オートコンプリート、コードスニペット、辞書登録、ショートテキスト展開、さらには音声入力など、ソフトウェア層の支援が入力効率の支配要因になりつつある。人間工学の改善もレイアウトよりキーボード形状(分割・テント・逆傾斜)やスイッチ荷重、リストレストの最適化の寄与が大きく、QWERTYのままでも十分に実現できる。つまり、レイアウト変更に賭けるより、QWERTYを土台に周辺技術を磨く方が、技術的に堅実で再現性の高い生産性向上策である。