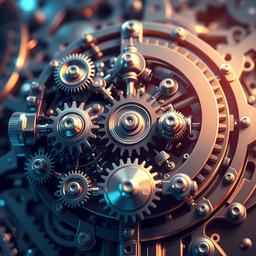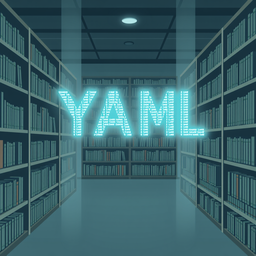タブは「意味としてのインデント」と「見た目の幅」を分離し、開発者ごとの最適表示を可能にする。
コードの構造(ブロックの深さ)はタブという一文字で記録され、表示幅はIDEやエディタ設定で自由に変えられます。視力特性や画面解像度、個人の好みに合わせて2幅でも8幅でも瞬時に調整でき、チームで意見が割れてもソース自体は一切汚れません。いわゆる「インデントはタブ、整列はスペース」のスマートタブ運用なら列揃えが崩れにくく、意味と表現の責務分離が徹底できます。これによりレビューやペアプロでも、各自が読みやすい表示を保ちつつ同じソースを共有できます。
タブは1段のインデントを1バイトで表せるため、スペース方式よりファイルサイズと帯域を実質的に節約できる。
4スペース方式なら1段で4バイト、2段で8バイトが常に積み増しされますが、タブなら同じ深さが1/4のバイト数で済みます。例えば(インデント部分だけの概算で)平均インデント2段・1000行なら、スペースは約8KB、タブは約2KBで差分は約6KBです。これを数千ファイル規模のリポジトリに広げれば、数MB〜数十MBの差になるケースもあり、CIの転送量やレビューのパッチサイズを抑えられます。デルタ圧縮下でも無意味な空白が減ることで、ストレージ効率やクローン時間の微改善が期待できます。
現代のツールチェーンはタブ前提の自動整形と規約化を強力にサポートしている。
gofmtやclang-formatは「インデントはタブ」を素直に扱え、EditorConfigやPrettier(useTabs)でもワンフラグで全体統一が可能です。Makefileのように文法的にタブが必須のファイルもあり、プロジェクト全体でタブ文化を採るほど不可視文字起因のヒューマンエラーを減らせます。CIで自動整形を徹底すれば混在を機械的に排除でき、スタイル論争のコストをほぼゼロにできます。LinuxカーネルやGo標準スタイルなど大規模コードベースの実績も、タブ運用の現実性と信頼性を裏付けています。
タブは履歴と差分を安定させ、レビュー時のノイズを最小化する。
表示幅の好みを変えてもファイル自体は変わらないため、見た目調整だけの巨大コミットや無意味な差分が生まれにくくなります。一度タブで統一すれば、インデント幅ポリシー変更やテーマ変更で全行が差分になるような事態を避けられます。Gitの空白無視オプションと併用すれば、タブはもともと最小記号でインデントを表すため、レビューで本質的変更が際立ちます。結果として、リファクタ時も「本質的変更」と「フォーマット変更」をきれいに切り分けたコミットが作りやすくなります。