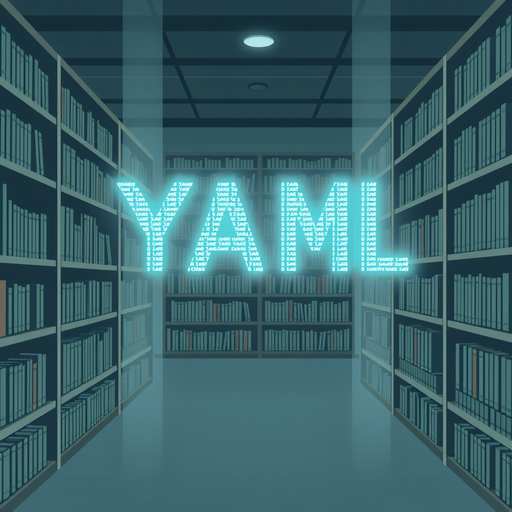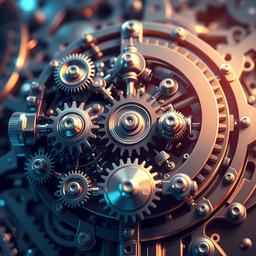JSONは小さな仕様と曖昧さのない文法により、実装間の互換性と相互運用性が極めて高い。
ECMA‑404/RFC 8259で定義されるJSONの仕様は約15〜20ページ規模に収まり、YAML 1.2の仕様書(80ページ超)と比べてもコンパクトで、解釈余地が少ないのが強みです。機能を絞った設計は、パーサの実装を収束させ、テストと検証のコストを下げ、エッジケースの発生を抑えます。API契約や設定ファイルでも暗黙的な型推論に悩まされにくく、長期運用での「微妙な違い」による事故を減らします。さらにYAML 1.2はJSONの上位互換でもあるため、JSONを選べばYAML側のパーサでも読めるという一方向の互換性メリットも得られます。
JSONはエコシステムの第一級市民として、言語・ランタイム・ツールチェーンの広範な標準サポートを享受している。
ブラウザのJSON.parse/JSON.stringifyや主要言語の標準ライブラリがネイティブ対応し、追加依存なく即座に使えます。PostmanのState of the APIや各種業界調査でも、公開Web APIの交換フォーマットとしてJSONが最も一般的と報告されており、OpenAPI/Swaggerなどの仕様やツールもJSONを中核に最適化されています。KubernetesのAPIサーバをはじめ、多くのプロダクション級プラットフォームが通信路としてJSONを用い、監視・テスト・モックの周辺ツールも豊富です。結果として、導入・学習・運用の総コストが下がり、プロジェクトの立ち上げとスケールが加速します。
JSONは“安全なデフォルト”を志向する設計で、デシリアライズに伴う攻撃面や予期せぬ解釈のリスクを最小化する。
任意タグ、アンカー参照、暗黙のスカラー型推論といった仕掛けを持たないため、入力データが思わぬ型や構造に化ける可能性が低く、セキュリティレビューの前提が明瞭です。パーサはデータ構築に専念でき、副作用的な拡張を避けやすいので、境界の明確なマイクロサービス間通信やゼロトラストなデータ受領にも向きます。運用現場では“まず安全に受け取れること”が最重要であり、JSONはその期待に素直に応えます。堅牢性を犠牲にせず、必要に応じてアプリ側で責任ある拡張を行えるのも利点です。
JSONは主要ランタイムでネイティブ最適化され、性能・可観測性・予測可能性に優れる。
V8やCPython、JVMなどで高速なパーサ/シリアライザが拡張なしに使え、GCや文字列内部表現と協調した実装が成熟しています。構造が明示的(括弧とカンマ)なためストリーミングやNDJSONのような逐次処理が簡潔になり、ログ基盤やETLでも機械処理が安定します。オーバーヘッドの見積もりがしやすく、SLOや容量計画に組み込みやすいのも現場的な強みです。さらにJSON Schemaと組み合わせれば、検証・型保証・エラーレポートのパイプラインを一貫化でき、品質と速度を同時に引き上げられます。