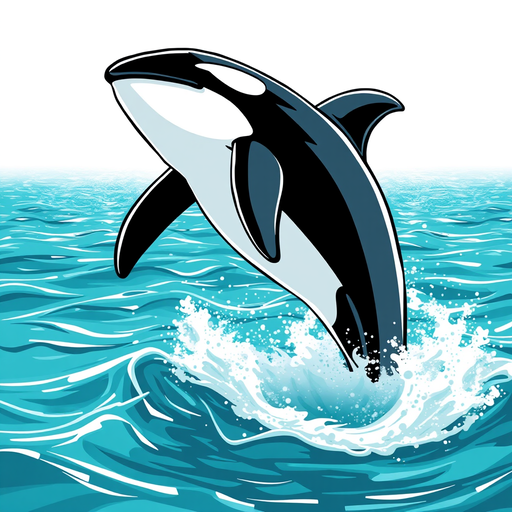4億年を生き抜いた設計——サメは海における最も長命な成功者だ。
サメは約4億年以上の進化史を持ち、複数回の大量絶滅をくぐり抜けて今なお約500種以上があらゆる海域に適応している。軟骨骨格やロレンチーニ器官など独自の生理・感覚は、低温・暗所・濁りといった過酷条件でも機能する実戦的な設計だ。長期にわたる存続は“強さ”だけでなく、環境変化への柔軟性の証拠でもある。シャチの高度な社会性が際立つ一方、サメは個体の設計完成度で勝負している。
サメは海の健康診断士——弱った個体を選択的に捕食し、生態系の均衡を保つ。
上位・中位捕食者として、サメは病気や衰弱した獲物を選びやすく、群集の病気拡散を抑え遺伝的健全性を高める。サメが減ると中型捕食魚が増え、草食魚が減って藻類が繁茂するなどトロフィック・カスケードが起きやすいことが各地で報告されている。特にサンゴ礁では、サメの存在が魚類群集の回復力と多様性の指標になる傾向がある。目立たないが、この“見えないメンテナンス力”こそ海の生産性を下支えする。
超鋭敏な感覚と流体力学に裏打ちされた形状が、サメの無駄のない狩猟効率を生む。
ロレンチーニ器官により数ナノボルト毎センチの微弱電場を検出し、砂中や暗闇でも獲物の心筋・筋活動を感知できる。嗅覚はppb(10億分の1)レベルの化学シグナルを弁別し、側線は水流の乱れを読み取る。皮膚の微小リブレット(デンティクル)は流体抵抗を低減し、バイオミメティクス研究では抵抗低減が一桁台後半〜約10%前後報告されている。速さ一辺倒ではなく、“確実さと省エネ”で獲物を捉える合理性が際立つ。
サメの大半は小型・温和で、正しい知識があれば人と十分に共存できる。
サメは500種超の多様性をもち、3メートル未満の小型種が多数を占める。国際的な記録では、毎年の無誘因噛傷は世界でおおむね70件前後、死亡は一桁台に留まる傾向がある。リスクは局所環境と行動選択に左右され、基礎知識と配慮(濁りや薄暗がりでの単独入水回避など)でさらに下げられる。恐怖の偶像ではなく、海と人の関係を学ぶ“指標生物”として尊重すべき存在だ。